「大学院で所属する研究室の選び方がわからない…」
「ブラック研究室だけは絶対に回避したい!」
「そろそろ大学のゼミ選びをしないといけないけど、選ぶ基準がわからない」
大学でのゼミや大学院での研究室を選ぶ時、何を基準に選んだら良いかわからないですよね?
とりあえず選んでみたけど、実際めちゃくちゃブラックじゃん…(泣)なんてこともしばしば。
研究室の選び方の極意とはなんでしょうか?
先に結論から話します。
「やりたい研究内容”だけで”選ぶのは絶対にダメです!!」
やりたい内容だけで選ぶとダメな理由があります。
その理由について、詳しく説明してきます。
この記事を読めば、何を基準に研究室を選ぶべきか、非常にスッキリすると思います。
Contents
研究室選びの基準における優先度

【研究室選びの基本】全く興味のない研究内容は論外
話を進める前に、軸となる前提を一つお伝えします。
それは、全く関係ない研究内容の研究室は選択肢に入れない。ということです。
当たり前ですが、これを念頭に置いて私の話に耳を傾けてください。
ここからは、先ほど述べた「やりたい研究内容だけで選ぶ」ことがなぜダメなのか。
その根拠をお伝えします。
研究室選びにおける研究内容よりも重要な基準
やりたい研究内容を重視して研究室を選ぶのはとても重要です。
さきほどと矛盾しているように思えるかもしれませんが、これは紛れもなく事実です。
ただ、ここでポイントなのが“重視して”というニュアンス。
やりたい研究内容ができるか?といった基準はもちろん重要。
ですが、優先度は少し低めに設定したほうが良いと思います!
※ただ全く関係ないことではなく、修士だと2年間、博士だと6年間も向き合っていく研究ですから、自分が知りたい!貢献したい!と思える研究をしてほしいと思います。

私も医療関係の大学院に行きましたが、研究内容もかなり重視して選びました。
研究テーマを考える作業が苦にならないといった利点があるからです!
では研究内容よりも重要な基準とは一体なんでしょうか?
研究室を選ぶ時はここを見ろ!【重要なのは3つだけ】

ここからは、やりたい研究内容よりも重視すべき基準について説明していきます。
本記事の核となる部分ですので、是非しっかりと目を通してください。
- 指導教授の人柄で選ぶ
- 研究室の実績で選ぶ(学会発表、論文出版数など)
- 自由度で選ぶ

上の3つを抑えておけばもう大丈夫。
この中でも自分なりの優先度をつけて選んでください!
研究室の選び方極意①-指導教授の人柄で選ぶ-
まず最重要項目として抑えてほしいのが、「人柄で選ぶ」です。
特に指導教授の人柄は、研究室全体の雰囲気を作りますので一番重要と言っても過言ではないです。
“人柄”と書きましたが、ただ温厚なだけではダメです。
- しっかりと話を聞いてくれるか(面倒見が良い)
- ハラスメントの噂はあるか
- 最新の技術に対して否定的ではないか(むしろ積極的に取り入れる)
- SNSを有効活用しているか
性格というより、こんな教授なら大学院生活がうまくいくといった観点から選んでいます。
最後のSNSを活用している教授は、実際にコンタクトをとってみると良いかもしれません!
(よく知らない学生に対してどのように対応してくれるかも見ることができます…!)
研究室の選び方極意②-研究室の実績で選ぶ-
続いて抑えるポイントは、「実績で選ぶ」です。
実績と一括りに言っても色々あると思います。
- 学会発表の頻度(受賞していれば尚良し!)
- 論文の出版数
この二つです!

たったこれだけでいいの…?
そんな声が聞こえてきますが、この二つだけで十分です!
その理由は至ってシンプルで、奨学金の免除審査や優秀学生の選考審査で見られるのがこの二つだからです。
つまり、”たくさん学会に出して、たくさん論文を書いている” と優秀な大学院生である、と判断されます。
どんなにすごい研究を一つ集中してやり遂げるよりも、数多くの研究に携わったほうが評価されます。(評価基準としてどうかと思いますが…)

私も実績基準で研究室を選びましたが、そのおかげで修士課程の間に学会発表4回(国内2回、海外2回)、筆頭論文2本とかなり実績を稼ぐことができました !
さらに、この実績のおかげで日本学生支援機構の貸与型奨学金の全額免除を勝ち取ることができ、100万円の臨時収入が得られました!!
なので、気になる研究室の所属学生がどれだけ学会発表しているか、受賞しているか、論文書いているか、の観点で研究室を評価していきましょう!
なるべく多くの業績を稼ぎたい方は、こちらの記事もおすすめです。
論文を読む、書く作業がかなり効率化されます!
研究室の選び方極意③-自由度で選ぶ-
最後は「自由度で選ぶ」です。
大学院や研究室を調べるとよく耳にするのが「コアタイム」です。
簡単に説明すると、 「この時間は研究室にいなければいけない」といった縛りの時間です。
私個人的な意見としては、コアタイムがある研究室はやめておいたほうがいいです。
理由としては、バイトや自己投資に当てられる時間が少なくなるからです。
中にはこんなツイートもありました…
コアタイムのメリットとしては、ある程度の強制力があるためサボりにくくなるところでしょうか。
ただ、強制力があるからといってやる気やモチベーションがなければ研究は捗りません。
自分でスケジュールを立てて計画的に進めたい、自由な時間がほしい、という方は コアタイムの有無を確認すると良いでしょう!
研究室の情報を入手するには?


研究室の選び方の基準はわかったけど、どこから情報を仕入れればいいの?
選ぶ時の注意点がわかっても、選ぶ際の情報がないと話になりません。
研究室の情報を得るには以下の方法があります。
研究室のホームページやSNSを見る
まず簡単にできる方法としては、気になる研究室のホームページやSNSを確認することです。
研究室自体のホームページやSNSが探してもない場合は、そもそもあまり良い研究室ではない可能性が高いです。
先ほど挙げた「①人柄 ②実績 ③自由度」のわかるところを確認していきましょう。
実際に確認できるところとしては、学会発表の報告や論文掲載のお知らせ、指導教授の活動などですね。
あくまでもホームページから確認できる内容で大丈夫です。

どの程度記事が更新されているかも見るべきポイントの一つです!
研究室の教授に直接メールで問い合わせる
ホームページを確認できたあとは、さらに深掘りして情報収集をしましょう。
少しハードルは高くなるのですが、直接メールで問い合わせるというのも一つです。
ハードルが上がるため、本当に興味がありホームページでの更新や活動内容がしっかりしている指導教授に限定して問い合わせてみましょう!
研究室の業績はネットから検索
研究室の業績は、簡単にネットで拾うことができます。
「学会 ○○(指導教授のフルネーム)」で検索すれば一発OKです!
多くの研究者は、Research Mapと呼ばれる自分の業績をまとめたサイトを持っています。
そのサイトから確認するのもよし、学会のホームページに飛んで確認するもよし。
検索情報が多くヒットする教授ほどアクティブに活動している証拠です。
ブラック研究室を避けるためには
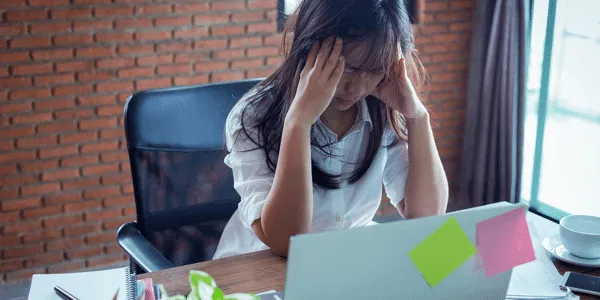
みなさんはこんな単語聞いたことがありませんか?
「ブラック研究室」
恐ろしい文字列ですね…。
ブラック研究室ってなに?
そもそもブラック研究室とはなんでしょうか?
少し調べてみて、ブラック研究室にもいくつかパターンがあることがわかりました。
- 束縛時間が長い
- 研究の成果を異常に求められる
- 相談できる人がいない
- 何をするにも放置される
- 人格否定される(モラハラ)
厳しすぎてもブラックですが、なにもされず放置されるのもブラックと言われるようです。
こう考えると、実際に指導する側も大変ですね…。(指導教授の皆様、お疲れ様です。)
【実際の声】ブラック研究室の実態
では、実際にブラック研究室にいた人たちはどう感じていたのでしょうか?
個人的にこの方の体験談は参考になると思いますので、ぜひご一読ください。
また、このような意見もあります。
本当にやりたい研究内容であれば、いくらブラックでも苦痛に感じない、という人もいるようです。
時間の縛りは興味でどうにでもなりそうですが、アカハラやモラハラは今後の人生にも響いてきますので、確実に避けていきたいところです!
ブラック研究室を見分けるには?
実際にブラック研究室かどうかを見分けるにはどうしたらよいでしょうか?
これは非常に難しいです。
ですが、一つだけかなりおすすめの方法があります!
それは、実際に所属している学生の声を聞くことです。
このような機会があれば、ぜひ色々聞いてみてください!
ですが内部事情を聞きすぎると不信感も出てしまうため、注意が必要です。
そんな機会ないよ!という方は、上で述べた①指導教授の人柄、②研究室の実績、③自由度の3つで判断していきましょう。
そこまで調べていれば、もしハラスメントがあった場合、情報として得られるはずです。
なにより「きちんと調べる」という過程が非常に大切だと思います!
まとめ
この記事では研究室を選ぶ際のポイントをまとめました。

研究室を選ぶのは良くも悪くもこの時期にしかできません。
自分のキャリア形成にも大きく関わってきますので、ぜひ慎重に吟味するようにしましょう!
また、こちらの記事では大学院進学後のお金の不安をなくすために、「大学院生のおすすめバイト8選」をご紹介しています。
研究室選びの後は、生活するための収入源を探してみるのがいいですね!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

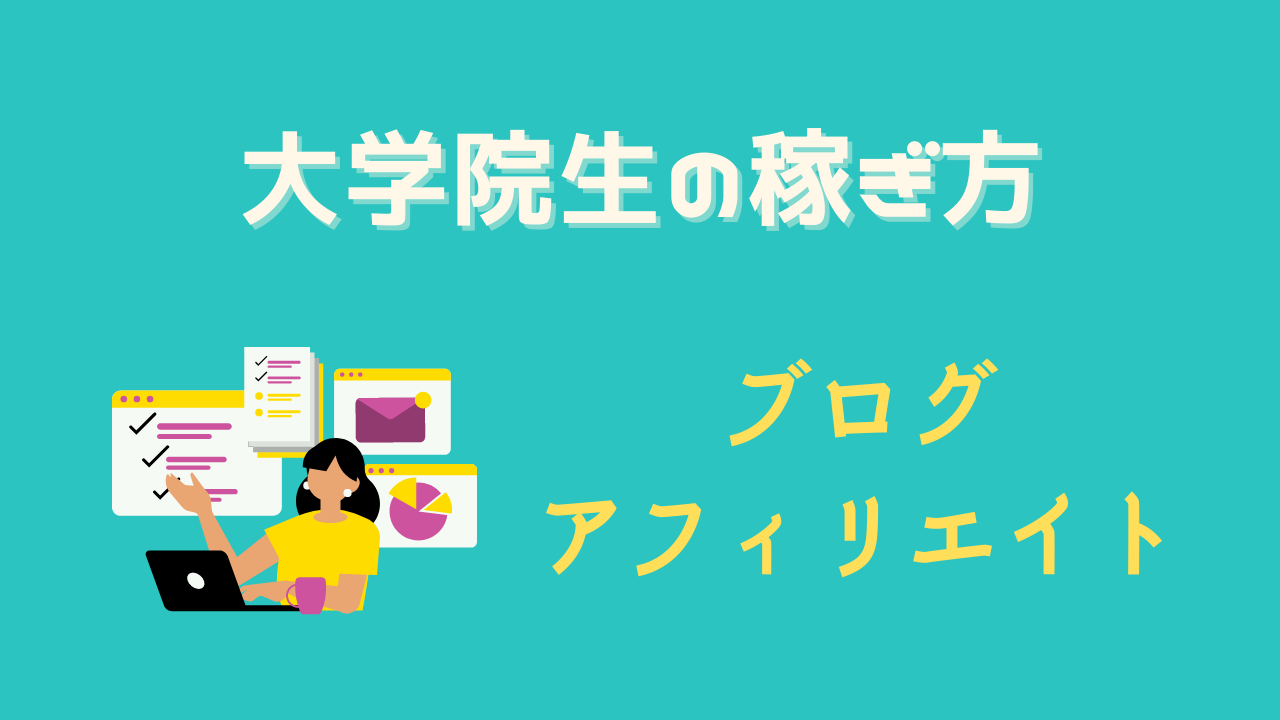
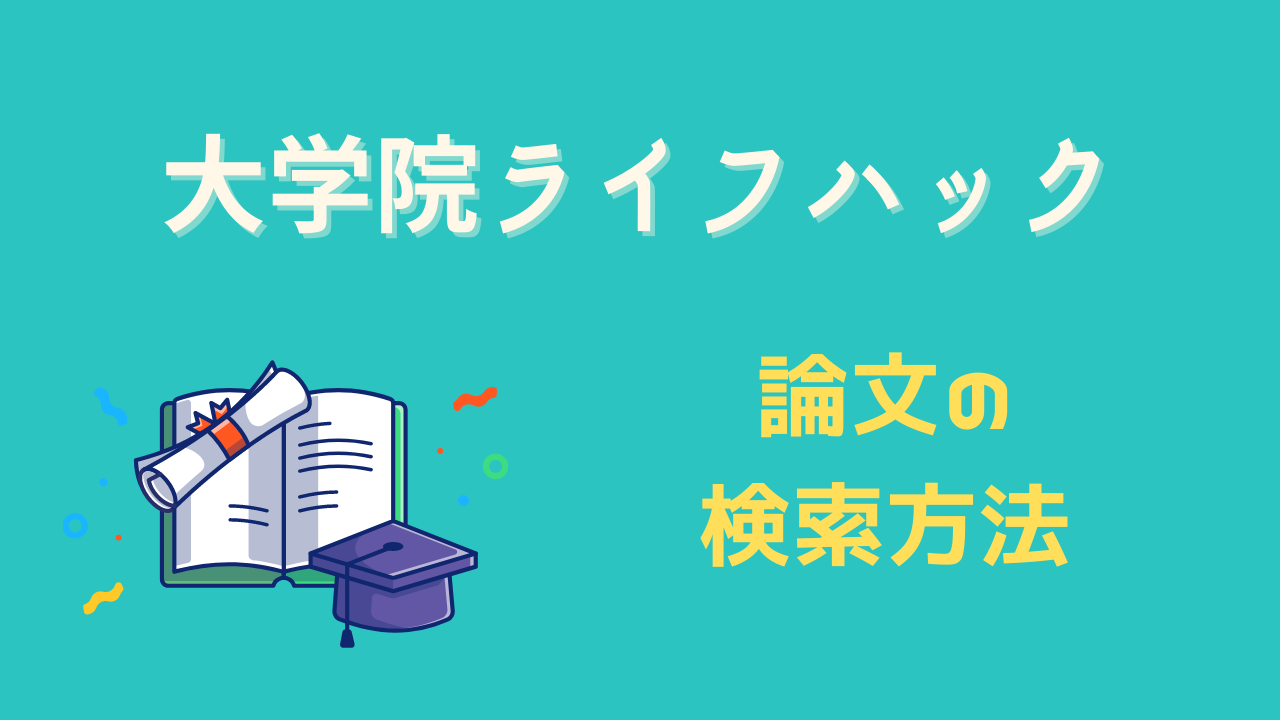
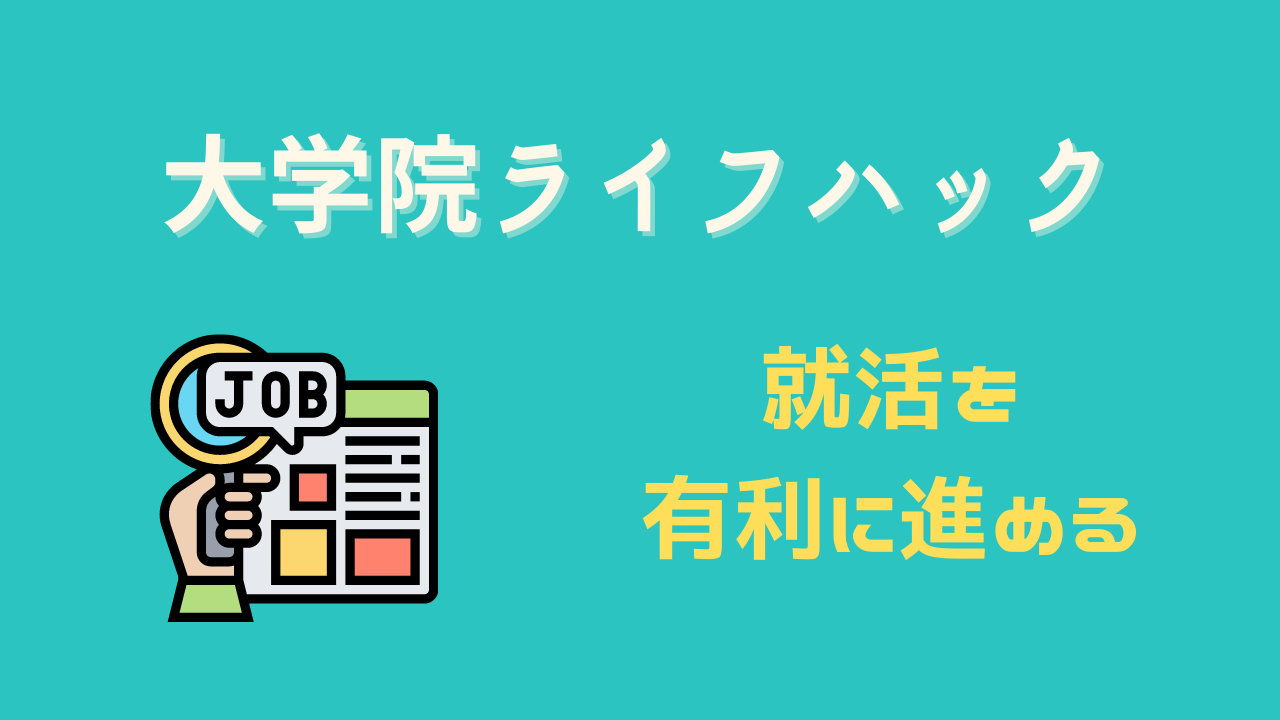
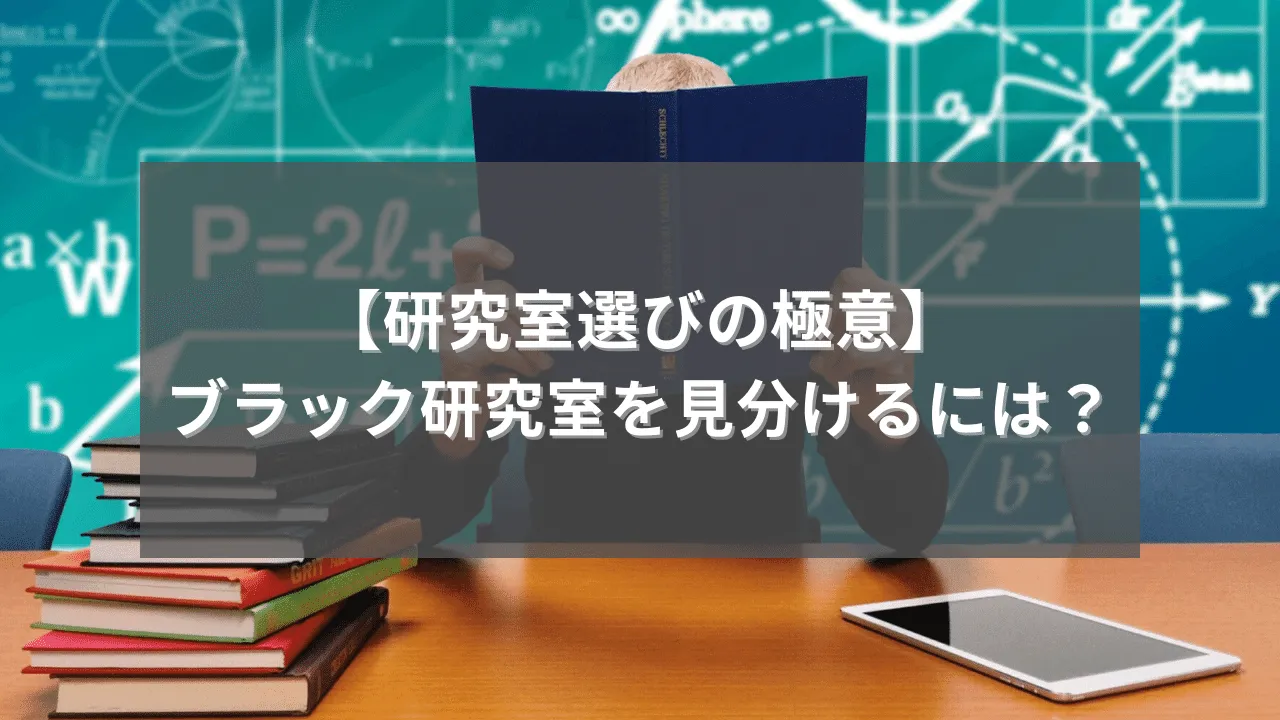

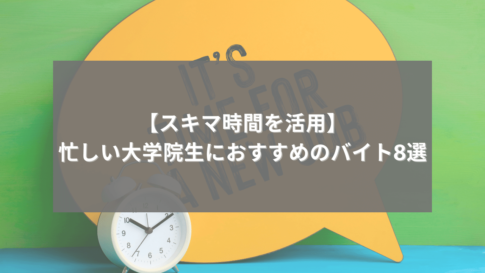
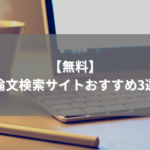


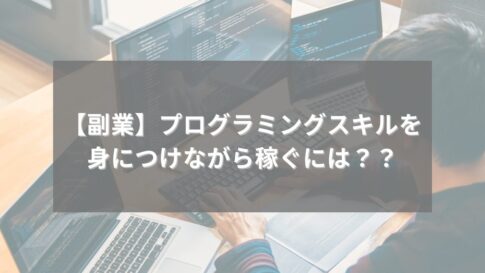

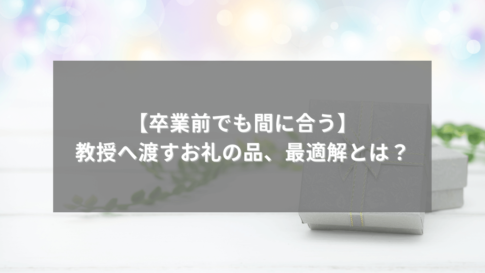
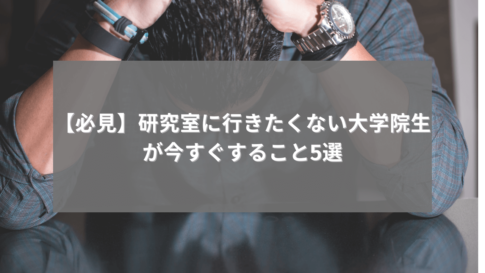

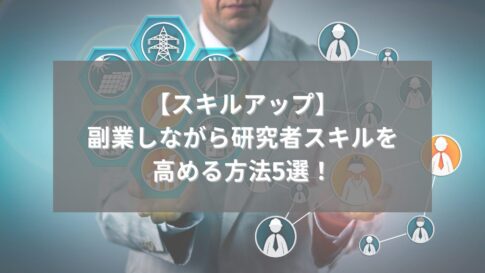
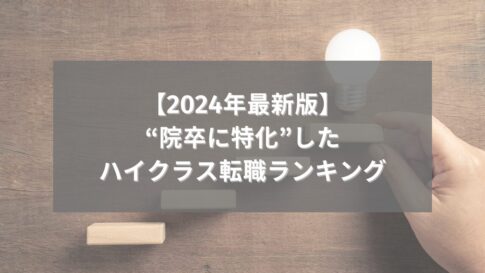
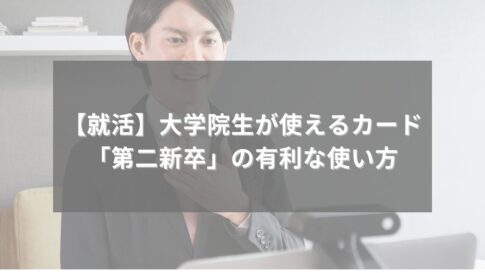
本記事を執筆しているぎぃぬです。
私も大学院の研究室を選ぶ時、何を基準にして良いかわからず悩んでいました。
後になって、もう少し考えておけばよかったな…と感じたことがたくさんあります。
そんな私だから伝授できる、研究室選びの極意についてお話しします!